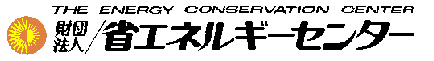・夏季・冬季の省エネルギー広報の強化、拡充
-
・学校教育における省エネルギーに関する教育の充実
- 児童生徒が省エネルギーを含む資源・エネルギー問題について理解を深めることは極めて重要であり、学校教育においては、従来から、児童生徒の発達段階に応じて、社会科や理科を中心に指導しているところであるが、今後とも、各学校において資源・エネルギーに関する教育の充実を図るとともに、担当教員講習会などにより環境教育についての教員の指導力の向上を図る。
- ・環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備推進
- 省エネルギーを始めとする環境への負荷の低減に対応した学校施設づくりの観点から、エネルギー・環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備の具体的な推進と実証的な検討を行うため、97年度からパイロット・モデル事業を実施し、児童生徒のエネルギー・環境教育に資するとともに今後の学校施設の整備充実を一層促進する。
- 児童生徒が省エネルギーを含む資源・エネルギー問題について理解を深めることは極めて重要であり、学校教育においては、従来から、児童生徒の発達段階に応じて、社会科や理科を中心に指導しているところであるが、今後とも、各学校において資源・エネルギーに関する教育の充実を図るとともに、担当教員講習会などにより環境教育についての教員の指導力の向上を図る。
-
・地方公共団体による省エネルギー活動の推進
- 97年度から、地方公共団体による先進的な省エネルギーの取組を促進するための補助制度を創設する。
- ・地方公共団体による地球温暖化対策の推進
- 地方公共団体が行う地球温暖化対策を目的とした事業のうち、
- 1)二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制・削減に効果が優れ、他への波及効果が高い対策
- 2)地域で取り組む地球温暖化対策についての計画を策定する事業に関して、その促進を図る補助制度を97年度に創設する。
- ・次世代都市整備事業の推進
- 省エネルギー、環境等に関連する技術のうち、都市及び都市システムに関連する技術を複合・統合化し、パイロット事業として現実の都市への適用を先導的に行い、次世代の都市システムとして社会的定着を図ることにより、新たな都市像・都市生活像を示す。
- ・情報化によるテレワークの推進
- 交通代替を通じた省エネルギーに資するため、モデル事業の実施等により、情報通信を活用したテレワーク等の在宅勤務やサテライトオフィスでの勤務の一層の推進を図る。
- ・「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画」(率先実行計画)の推進
- 率先実行計画に規定するエネルギー利用の節約目標の達成に向け、国の各行政機関が積極的に省エネルギーに関する取組を推進する。このため、97年から、「物品等の調達に係る推奨リスト」の検討や「職員が業務に用いる共用自転車の導入の可能性について」の検討を進める。
- 97年度から、地方公共団体による先進的な省エネルギーの取組を促進するための補助制度を創設する。